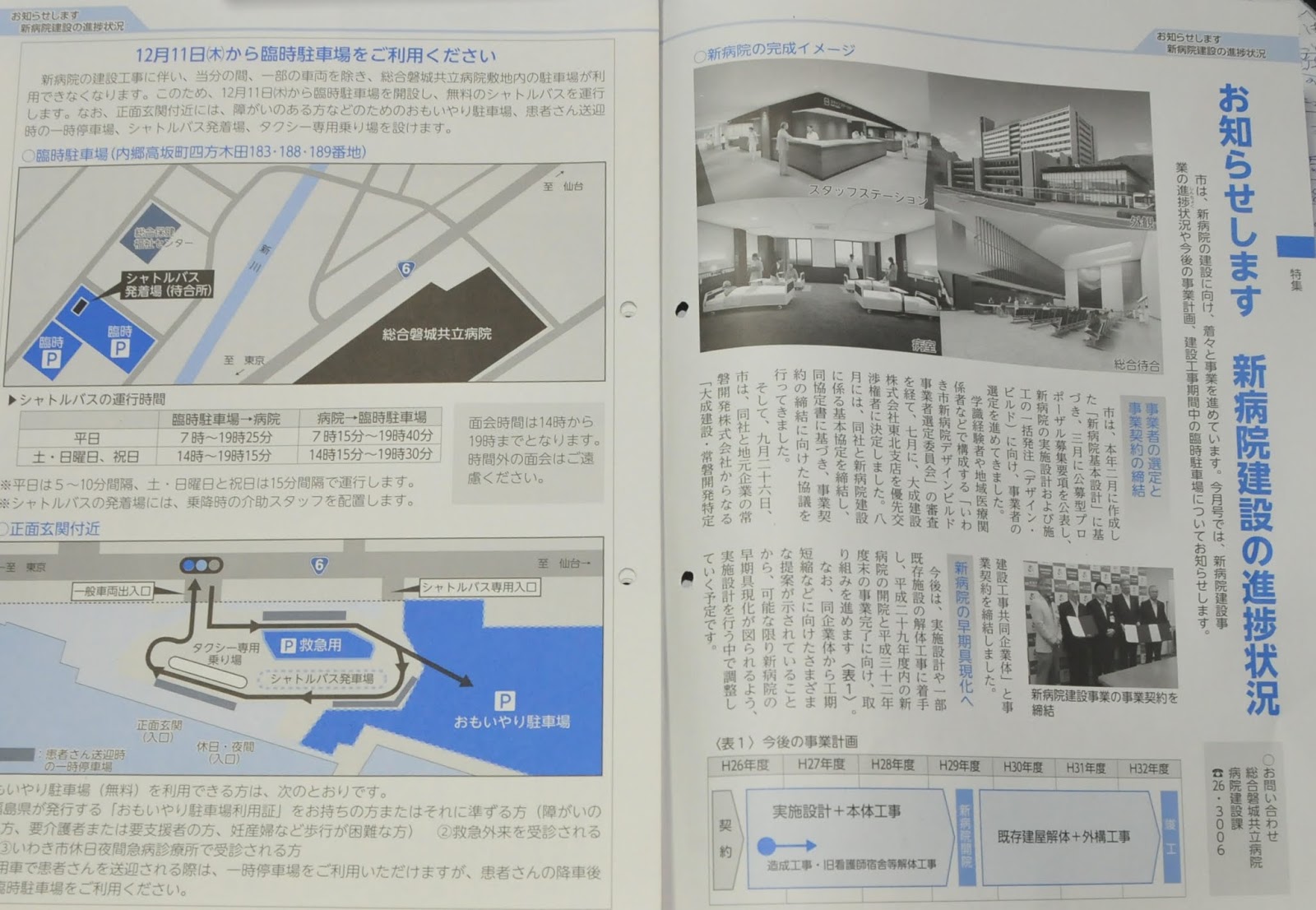近所のおじ(故人)の家に甘柿がある。今年は生(な)り年だ。だいぶ色づいてきたので、連休明けの11月4日夕、1回目の柿もぎりをした。丸ごとかじったり、八つ割り=写真=にして酒のつまみにしたりした。
去年11月に甘柿のことを書いた。――会津の後輩が甘柿を送ってきた。八つ割りにして晩酌の膳に添えた。いわきの甘柿も食べた。市の風評被害払拭プロジェクト「見せます!いわき情報局」に当たって、一般的な傾向を見た。柿はいずれも検出下限値(キロ当たり10ベクレル未満)か、それを少し上回る程度だった――。
今年は今のところ、会津も、中通りも、いわきもほとんどが「検出されず」だ。キノコと違って柿とは気持ちよく向き合える。熟しかけたものもあれば、硬いものもある。硬めの柿はさっぱりした味だった。
ベクレルなんか意識もしなかった6年前には、こんなことを書いた。――新聞に「柿の日」の記事が載っていた。正岡子規の「柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺」は10月26日に詠まれた。それで、全国果樹研究連合会カキ部会がその日を「柿の日」と制定したという。
甘柿の幹はそんなに太くない。梢もそう高くない。なんとも中途半端な木だ。脚立を立て、柿の幹を支えに爪先立ちをして、手でもぎとれる範囲内で実を収穫した。手籠にいっぱいになったところで、手が届かなくなった。半数以上が残った――。
今年も同じように、まだ3分の2が残っている。2回目はコアラになってもぎるとしよう。ほんとうは孫を呼び出して一緒にもぎり、一緒にかぶりつきたいのだが……。へたな五七五にすると、こうなる。「甘柿をもいでも孫にあげられず」