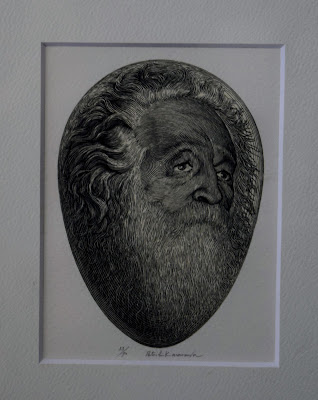台所と茶の間の境に戸がある。開け閉めがめんどうなので、戸は開けたままにしてカーテンをつるした。
台所から茶の間に戻るときには、スリッパを脱いで敷居(しきい)をまたぐ。段差は2センチほどだろうか。
ある晩、銚子とポットを運んだあと、また台所から酒のつまみを運ぼうとして、敷居に足を引っ掛けた。あれっ! 前のめりになって宙を飛び、六法を踏んだ。いやー、転ばないでよかった。
前から自覚してはいたことだが、ジイバアの日常はトンチンカンの連続だ。若いときと違って、体も思うようには動いてくれない。
前は余裕でこなしていたことが、なにかが足りなかったり、欠けたりする。それを、そばにいる人間が気づいてフォローする。「2人で1人」。もはやトンチンカンだらけで笑うしかなくなった。
一方で、いかにも年寄りじみた趣味がぴったりはまることもある。正月三が日の最後の日、道路向かいの奥にある故義伯父の家で昼食をとった。
火鉢を出す、木炭をくべる、金網をかける。そこで年末にカミサンの実家でついた白もちと豆もちを焼いた=写真上1。それがジイバアの昼食だった。
言われたとおりにして、海苔(のり)に包んだもちを四つ食べた。若いときは、四つではもたなかった。もっと、もっと――となった。
午後3時には“孫”が母親とやって来る。昼食をとったあとは家に戻って昼寝をし、調べものをして過ごした。
上の“孫”は大学を出て社会人になった。下の“孫”は大学生だ。来るとすぐ、いろいろ近況を報告してくれた。そのうち、母親が「私らも銀婚式を迎えました」という。“孫”の年齢を考えればそうなるか。
すると、私らは? カミサンが「今月で金婚式」と応じる。えっ、50年か――。そのあとに続くカミサンの言葉は省略する。
長いと言えば長い道のりだが、あっという間の半世紀と言ってもおかしくない。なかでも震災はこの半世紀のなかで最大の出来事だった。
日常への向き合い方がガラリと変わった。「野原を断崖のように歩く」。作家開高健の言葉が胸にしみた。
当たり前の日常=野原は、実は当たり前ではなかった=断崖だった。断崖を野原のように勘違いして歩いていた。断崖が日常の本質なのだ、いつ転げ落ちるかわからない――ということを胸に刻む出来事だった。
ジョン・レノンが描いたヨーコと自分の肖像画の下に、英語で「ツー・イズ・ワン」とある。「2は1」、あるいは「2人は1つ」。こちらが考える「2人で1人」は、レノンの世界から離れて福祉的な意味合いが濃い。
カレンダーを見てフッとそんなことを思い出していたら、正月にやって来たファミリーから宅配便で花束が届いた=写真上2。ピンクを主体にした、上品な色合いにカミサンが感激していた。ありがたいことではある。