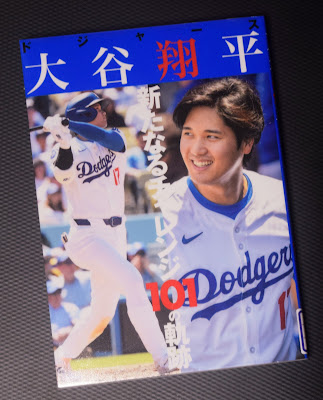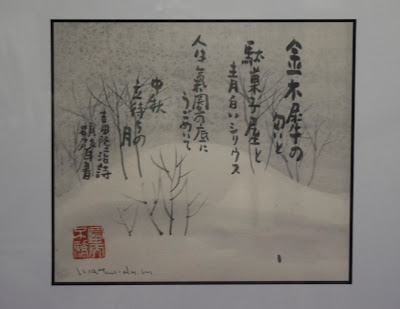お福分けのハヤトウリの話(11月29日)の続き――。この秋も後輩から季節のお福分けが届いた。9月初旬の青パパイアが最初だった。
後輩はビニールハウスでパパイアの栽培を始めた。今は自宅裏に広がる畑で露地栽培をしている。
フェイスブックに投稿した文章によると、露地栽培に挑んで3年目になる。試行錯誤を繰り返しながら、年々栽培本数を増やしているという。
先日、四倉町塩木の仁井田川沿いで、パパイアの露地栽培を手掛けている人の話がいわき民報に載った。
いわきの人間にとっては、青パパイアは新しい食材だ。その栽培に挑む人間が複数いるというだけで、趣味を超えた「業」としての広がりと可能性を感じるようになった。
まずは縦に割って未熟な白い種を取り除き、ピーラーで皮をむいたあと、カミサンに頼んで炒め物にしてもらった。
晩ごはんのおかずになって出てきたが、やわらかくて、さっぱりした食感がごはんに合った。
青パパイアのあとは落花生、それから日をおいてフェイジョア=写真、はちみつなどが届いた。
落花生は「おおまさり」。殻ごと塩水でゆでた。ホクホクしてやわらかかった。乾燥して硬い落花生は子どものころから口にしているが、生をゆでて食べるという発想は、若いときにはなかった。
それを知ったのは7年前だ。平・本町通りで「三町目ジャンボリー」が開かれたとき、好間の生木葉ファームが出店し、勧められるままに生の落花生を買った。
3%の塩水でゆでるといい、といわれた。晩酌のつまみに塩ゆで落花生が出てきた。殻を取ったピーナッツの硬さしか知らない人間には、枝豆のようなやわらかさが衝撃だった。ほくほくして、ほのかな塩味が効いていた。
フェイジョアも、いわきの人間には新しい果物だ。自然に落果したものを追い熟させてから食べる、とネットにあった。
手に取ると少しやわらかくなっている。それを四つに切って、果肉をスプーンですくって食べた。ほのかな甘さが口の中に広がった。
ほかにも、カミサンの知り合いが柿やリンゴやミカンを持って来た。今は晩酌を控えている。で、晩ごはんのあとに果物が出てくる。
ある晩は、ゴボウとニンジンのきんぴら、あるいは煮魚といった具合に、カミサンは「手抜きができる」と喜んだ。
スダチを袋にいっぱいもらったこともある。さすがにわが家だけでは使い切れない。カミサンがあちこちにお福分けをした。
『徒然草』に「よき友」の話が出てくる。第一番が「物をくれる友」だ。消費生活は「売り買い」だけでなく、お福分けの循環にも支えられている。安く貧しくなった日本では、この循環がますます大事になる。