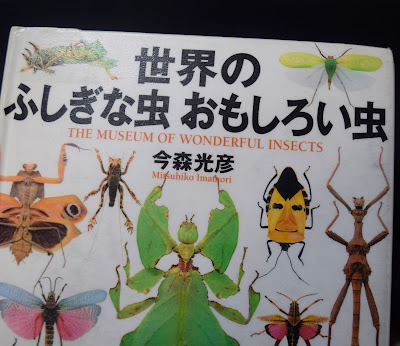立春を機にアルコールを再開した。日本酒をそば猪口で2杯。これを1時間以上かけて飲む。いや、なめる。
ドクターからは一般的な目安として、日本酒は1合、焼酎は0.6合、ビールは500ミリリットルまで、といわれている。
そば猪口にはおよそ0.4合入る。量でいえばビールだが、チビリチビリではおいしくない。後味とのど越しのやさしさから日本酒にした。
断酒していたときには、晩の食事はものの15分もたたないで終わった。現役時代の「早めし」の癖はなおらない。
朝は台所のテーブル、昼と晩は茶の間のこたつで食事をとる。おかずの白菜漬けは私が甕から出して切る。
晩は食べ物をお膳に並べてこたつに運び、昼と同様に片付けをする。それ以外はカミサンにお任せだ。
当然、箸を持つのは私が早い。カミサンが席につくころには、もう終わりかけている、ということもある。
晩酌が復活したおかげで、それがなくなった。カミサンの食事が終わっても、まだ酒をなめている。
早めしどころか、だらだらと1時間余り、つまみをほおばりながら、ほろ酔い気分に浸って……。そんなほぐれた時間にブログの下書きをつくる断酒前の習慣も復活した。
下書きづくりもコロナ禍で変化した。コロナ禍の前は、下書きをつくって晩酌を終え、寝る前に入力して早朝、清書したのをネットにアップする、というやり方だった。
コロナ禍が起きると、ブログの新聞(古巣のいわき民報)転載が始まった。活字になって残る怖さがよみがえり、今は一日早く、日中にブログを仕上げるという、現役並みのやり方に替わった。
チビリチビリやりながら原稿の骨組みをつくる。すると、気持ちも開放される。そんなときのつまみは軽いものでいい。
量ではない、少なくてもいいからいろんな味を楽しみたい――。酒の専門店へ行って、つまみも調達するようになった。
で、ある晩にはチーズやクッキー、ポップコーンなどが並んだ=写真。別の日には干し柿やブロッコリーのドレッシング、そして残りのチーズが。
日曜日は刺し身がメーンだ。晩酌を再開したのは、刺し身を楽しむためでもある。2月の前半には早くも今年(2025年)の「初ガツオ」を口にした。
今はカミサンの要望を聞いて、メジマグロやヒラメ、タコの盛り合わせにしてもらう。ヒラメはカミサン用だ。
日本酒ではなく、焼酎を適量の倍以上飲んでいたときには、そばにお湯入りのポットを置いていた。
糖質・プリン体ゼロの焼酎をなめ、すぐお湯を口に入れる。いわゆるチェイサーで、胃の中でお湯割りにした。
それが懐かしいわけではない。が、今は日本酒に含まれている糖質・プリン体が足の親指にどう作用するか、様子見といったところでもある。