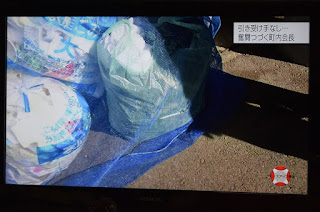裏の義弟の家の物置を整理していたカミサンが、またまた“化石”を掘り出した。とっくに忘れていた10~20代の遺物だ。
社会人になってすぐ自費出版をした詩集『受胎前後』が10冊ほど。ほかに、同人誌「無伴奏」。平(現福島)高専時代、先輩2人と出した3人詩集『顔』(昭和41年発行)は、読むに耐えないから、即、本棚にぶちこんだ。
懐かしかったのは、いわき市のタウン誌「PeBe(ぺぇべぇ)」=写真。創刊号は1976(昭和51)年8月1日発行とある。発行人は現・ギャラリー界隈オーナー、編集人は私の友人・後輩など3人(2人はもうこの世にいない)。題字は若い林和利クンが担当した。
ちなみに、「ぺぇべぇ」はいわき語の「~だっぺ」「「~だべ」の語尾から採った。つなぐとフランス語風の味わいがある
題字の林クン、いや現姓松本クンは今年(2015年)夏、いわき市立美術館ロビーで、「神々の彫像 アンコール・ワットへのみち展」に併せ、「ニュー・アート・シーン・イン・いわき 松本和利展」を開いた。個展開催中に再入院した。
ざっと40年前、草野美術ホールにたむろする20~30代の人間が、同ホールを事務局にして、文化情報誌を出そうと意気投合をした。それぞれが仕事を持っているので、アフターファイブの“余力”で雑誌づくりにかかわった。私も仮名で巻頭コラムを書いた。表紙を松田松雄の絵で飾り、松田をホストにした対談<松田松雄の「ん・だもんだ――長靴対談」>を雑誌の目玉にした。
<長靴対談>というタイトル名は、松田が雨の日ばかりか晴れの日も長靴をはいていたことから生まれた。<ん・だもんだ>は岩手・陸前高田の方言かどうかはともかく、なまりの強い松田のシンボルとして使った。松田が画家としていわき市民に評価されるようになったことが、根っこにあった。画家だからこそ、ほかの人間もまた仕事を持っているからこそかかわれる文化運動がある。
月刊の触れ込みだったが、そのへんは2カ月になったり、3カ月になったりした。10号で松田は対談を終了し、11号から表紙絵も教え子の作品に替わる。12号以降がないので、11号のあと発行されたかどうかはわからない。たぶんそのあたりで廃刊になった。
10号の対談相手は当時の田畑金光いわき市長。松田が事務局長を務める「市民ギャラリー」がいわきに美術館を――という運動を展開していたことは、当然、承知している。
それを踏まえて「これからの社会は、開発志向型じゃなくして人間を大事にするという福祉優先、文化優先。そういう意味で文化都市づくり、そういう方向に重点を移していかなければいけないと考えている訳です」と言明している。同市長の決断で7年後の昭和59(1984)年、市立美術館が開館した。
松田にはこういう一面もあったということを、ほんとうは今、故郷の岩手県立美術館で11月29日まで開かれている松田の回顧展で見せたかったなぁ。